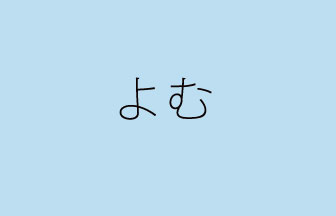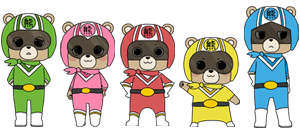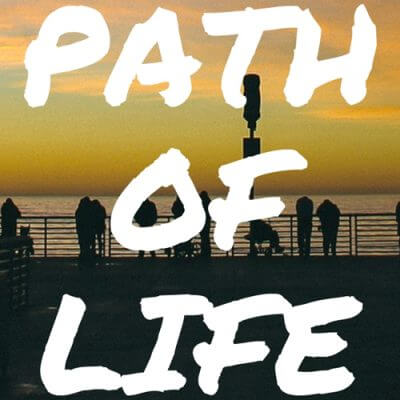歩道を歩いている私の背後から、エンジン音を轟かせ何かが接近してくる。私の横には泥水が寄り集まっている。その場を小走りで通り過ぎるも直後に、豪快に辺り一面に水が叩きつけられる。
スカートの裾が黒く染まっていた。
六月。埼玉県熊谷市。熊谷農業高校前。梅雨真っ盛りであった。

目の前には、私と外界とを隔てる扉がある。私は決断力に欠けた。私と外界を混ぜ合わせた際の不幸を妄想してしまい、その場で立ち尽くしてしまうのだ。
熊谷農業高校生活技術科一年。つまりは、その一員となるための扉があるのだ。
私の葛藤とは裏腹に、扉はいともたやすく音も無しに開かれた。担任である背の高い男がぬっと目の前に現れ、私を教室の中へと招き入れ、自己紹介を促した。
私は教卓の後ろで背を丸め、できるだけ身を縮めていた。恐る恐る室内を見渡すと三十は軽い人間の視線を感じた。反射的に視線を伏せると、席が一番近い女子と目が合った。また慌てて、体を反転させると黒板と顔が合った。もし眼前に見えるのが鏡であったなら、熟れたトマトでも映っていたことであろう。
チョークを持ち、線を踊らせながら私の名前を板書する。再度体を反転させ、目線は教卓に落とした。
「宮沢冴恵です」
小鳥の囀りの方が鮮明に聞こえただろう。しかし私には室内の静寂も相まり、私の無愛想な声が教室に響き渡ったものに思えた。
そして・・・・・・間。誰しもこの一瞬だけは神経が研ぎ澄まされ、コンマ一秒をじっくりと堪能できる。
単純明快。一言で済む自己紹介はこの空間ではあり得なかった。
学生達は皆、急に餌を取り上げられたハムスターのように、表情を貼り付けたまま固まっていた。
もし今、窓へと目を向けたなら、落ち葉は空中で止まり、羽虫は飛び方を忘れたように羽を止め、呆けた顔で私を見つめているのだろう。
私と外界とを隔てる扉は決して、教室の扉なぞではない。常に私の目の前にあるのだ。
私以外は、既に熊谷農業高校生活が始まって二月程経っているはずなのに、未だ周囲との距離感を測っている者が多かった。
昼休憩を示すチャイムが鳴ると、一斉に露骨なグループ分けがされた。あぶれた者は自らの机に張り付き、打ち解けている者達は一箇所に集まる。私を中心とした半径一メートル以内に人影は無かった。転校生という『普通』の学生なら喜んで食いつくであろう格好の餌に、誰も釣られないことがあるのだと思い知らされた。
今になって、私は赤の他人の椅子に座っている気がした。常に目線を感じ、小声の会話に耳が敏感に反応してしまう。一旦、心の奥底でこの空間を拒否すると、ひたすらに窮屈で、心臓が縮み上がった。こんな場所で食事をとるという恥を晒すのは御免であった。生活感こそが最大の恥なのだ。
バッグから袋を取り出し、必死に周りを見ないように教室を後にする。少しでもストレスがない環境に行きたかった。
「宮沢さん!」
突然、爽やかな声に呼び止められた。恐る恐る振り返るとそこには、湿っぽく膨張する髪は耳元で揃えられ、私より頭ひとつ分背の高い、快活な印象の女子がにこやかに立っている。
私は間違っても価値観が正反対な人間、つまりは『普通』の学生に声をかけられることはない。だから、彼女が何の目的で私に笑顔を振りまくのか想像がつかなかった。
彼女が私の顔色を伺う一瞬に、私はあっさりと思考の海に溺れた。口元は空気を欲する鯉のように蠢いている。しかし、私の醜さに彼女はあくまでにこやかに助け舟を出すのであった。
「同じクラスの久下だよ。久下真仲」
「あっ」と喉で止まっていた声が抜けた。目を合わせるのが怖くて、クラスメイトの顔すらまだ覚えていなかった。
「あのさ、お昼一緒に食べない?」
彼女、久下真仲さんはビニール袋を目の前に掲げて見せた。
吃音のみ発するこの口は、どれ程意識しようが、会話の速度に思考が追いつかない限り、呼吸しかしてくれない。
いくら思慮しても最適な答えは出ず、結局、捻り出した言葉は素っ気ないものであった。
「うん」
その一言だけで久下さんは口角を少し上げ、私の手を取り「良い場所があるよ」と案内をしてくれるようだった。そんな中、教室の扉から怪訝な表情を見せる女子達を確認し、私は大変後ろめたい気持ちでいた。
少しカビ臭い空き教室にいた。久下さん曰く文芸部の部室なのだという。窓付近の椅子に腰掛け、互いに対面する形で机に昼ご飯を広げた。私は母が多忙のため甘食パンである。対する久下さんもパンであった。生徒の多くは親の手作り弁当である。その中でコンビニパンは女子であれば多少は奇異の目で見られることになる。久下さんが私に積極的に絡む理由がわずかだが分かった気がする。
その後はパンをつまみながら、高校受験の面接を想起させる会話を数度し、教室へと戻った。
私は担任に呼び出され、職員室に居た。部活見学の説明と、ありきたりな教訓をいただいた。部活への熱は生憎持ち合わせていなかったため、文化部の幽霊部員にでもなろうかと廊下へ出ると、久下さんがいた。
「ねえ、ちょっと付き合ってくれない?」
横目で辺りを見回す。カウンターやテーブルは発色の良い木目調で整えられ、壁は無骨に塗り固められている。吊られている淡い光を放つ電球からはクラシカルな印象を受ける。
熊谷農業高校正門から出て、真隣の熊谷高校正門を通り過ぎて少し歩くと、大きな通りにぶつかる。周りには如何にもな、町のにおいが染み付いた建物が並ぶ中、唯一真新しく目につく店がある。私と久下さんはそこにいた。
目の前には人気メニューらしい、小ぶりではあるが厚く、放っておくだけで蕩けてしまいそうなパンケーキがある。久下さんは慣れた手付きで切り分け、生クリームを付けて頬張る。
「ん~!おいし~!」
久下さんは過剰なくらいに幸せな表情をした。その緩んだ唇についた生クリームを、私はまじまじと眺めていた。随分と眺めていたせいであろう、久下さんは苦笑し、唇を舌先で舐め取った。
「今日は、私たち以外に学生いないみたいだね」
「けっこう珍しいんだよ」そう付け加えて、久下さんはまたパンケーキを口に運んだ。会話よりも食事を優先している。明らかに、まだ一口も食べていない私に気を使っていた。
私は『大人っぽさのために見栄を張る』同年代を目の敵にしている。だからこんな雰囲気のある場所には近寄らなかったし、パンケーキなんて食べようとも思っていなかった。
しかし久下さんに申し訳ないと思い、食すことにした。ナイフは想像通り流れるようにパンケーキを切り分けた。食器を通して食べ物の食感が分かってしまうのは、多分、そうある経験ではないだろう。生クリームを少し付け、頬張った。
「おいし・・・・・・」
久下さんはいつの間にか私を見ていた。その口は段々と湾曲し、にやと微笑む。
「でしょ~!」
待っていましたと言わんばかりに、久下さんはこのお店のことを語り始めた。今日が初対面であるはずなのに大変楽しそうで、表情が良く動く。釣られて私も口尻が歪んだ。彼女は更に歓喜の色を増したのだった。
その後は他愛の無い会話をし、空が黒ずむ前に解散となった。現在、私の視界には真っ白な、まだ見慣れぬ自室の天井が広がっている。
久下さんは文芸部の部員であった。部活を決めかねていると言うと、間を開けず文芸部を紹介してくれた。明日は文系部にお邪魔することになった。
ふと、今日の反省会は暗い雲が差していないことに気付いた。枕を濡らす日が連続することもある、一番精神的に弱る時間帯であるはずなのにだ。新たな学生生活の不安は尽きないが、それでも脳裏に蘇るのは、久下さんの気遣うような笑顔であった。
著者紹介
- 名前
- エンガワ
- コメント
- 脚本、小説共に勉強中。ツーリングと聖地巡礼のために生きてます。